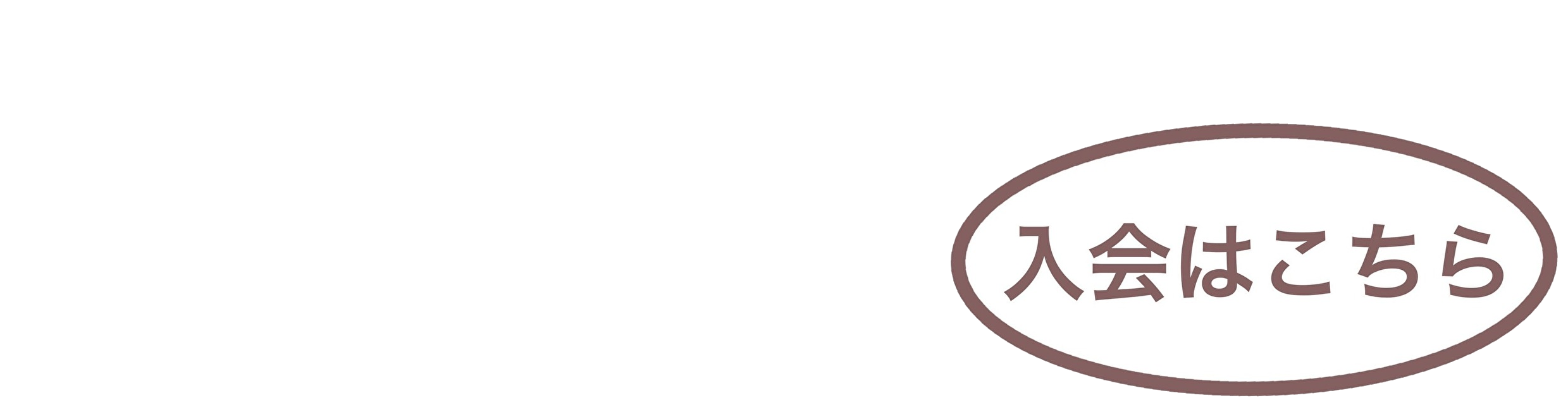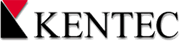教育講演
-
ジルコニアインプラントの現状と表面改質
愛知学院大学非常勤講師(教授級)
伴 清治 先生
整形外科領域では、ジルコニアの優れた化学的・生物学的安定性および摩耗特性を活用し、人工股関節の骨頭として、1990年代より用いられている。歯科領域では2000年代始めより歯冠修復物として利用されてきたが、インプラントフィクスチャーとしても利用が進んでいる。現状の歯科インプラントの95%はチタン製であるが、審美性の追求およびアレルギー対策としてもジルコニアインプラントが注目されている。あるヨーロッパメーカーの調査において、250人以上の患者にチタンインプラントとジルコニアインプラントの治療後の症例写真を見せ、どちらを選択するかというアンケートをとると、チタンインプラントを選択したのは10%、ジルコニアインプラントを選択したのは35%であったと報告している。日本ではジルコニアインプラントは歯科医療材料として認められていないが、欧米では既に多くのジルコニアインプラントが販売されている。当初は、1ピースタイプのみであったが、2ピースタイプのジルコニアインプラントも一般化している。
ところが、ジルコニア表面は疎水性であり、バイオイナート(生体不活性)素材に分類されており、骨との接触部位では骨と結合できる表面改質をする必要がある。骨と結合するためには基本的に親水性が望まれ、多くの方法が提案されており、市販の歯科用ジルコニアインプラントは様々な表面改質方法が採用されている。決定的に優れているという方法はなく、各メーカーで独自の方法が用いられており、発展途上といえる。
これらのジルコニアの表面改質は、粗面化、表面活性化、コーティングの3つの方法に大別される。適切な表面改質により、骨との良好な結合が長期に得られるという報告が多くなっている。日本においては、ジルコニアインプラントは未認可であるが、個人輸入により臨床使用されている例があると聞いている。今後、早期の認可が期待され、ジルコニアインプラントの最新情報に注目しておく必要がある。今回は、ジルコニアの表面改質と歯科用インプラントへの応用の現状を説明する。 -
咬合医学的視点から見た新しい咬合の概念
神奈川歯科大学 咬合医学研究所 所長
佐藤 貞雄 先生
歯科医療においてなぜ咬合の概念が必要なのか、これは長い間の歯科医療における疑問である.答えは簡単である、それはわれわれには患者がいるからであり、患者は咬合治療を求めているからである.また患者は自分の健康に強い関心があり長期に健康を維持したいと願っているからというのも理由の一つであろう.しかし答えは一見簡単であるが治療上これを実践し、長期に亘って患者のQOLに貢献するのは簡単ではない.
歯科咬合学的にはバランスド咬合に始まりグループファンクション咬合や犬歯誘導咬合など多くの咬合の概念が過去提案されてきたが、なお混乱があるのが実情である.なぜ混乱があるのかというと、それぞれの概念がクリアーに定義されていないのが大きな理由であり、また咬合誘導(オクルーザルガイダンス)を必要とする咀嚼器官の機能が曖昧なままで咬合構築をしようとするからである.すなわち、患者ごとに適切な誘導路が与えられないまま治療を終了するということが多く、それゆえに咬合の崩壊や歯周疾患の増悪、顎関節症の発症、全身的症状の発症など極めて残念な結果を生みだしている.
咬合医学的に咀嚼器官は、極めて特殊に進化してきた機関で咀嚼、発音、嚥下、呼吸、姿勢の維持、審美、ブラキシズムなど多くの機能を持っているが、なかでもブラキシズムはストレス-自律神経系と密接に関連して生体のホメオスタシス維持の役割を果たしている(ストレスマネージメント).このことから考えると、咬合を考える基本はブラキシズムにおけるグラインデング運動であることが分かる.また、与えるべき咬合平面や咬合誘導路は患者毎の骨格形態や顆路角によって異なっている.それゆえにこれらのことを踏まえ患者毎に適切な咬合を与える必要がある.デジタルデンティストリーの近未来― データベース基盤型補綴歯科治療
公益社団法人 日本補綴歯科学会 大会長/昭和大学 歯科補綴学講座 教授
馬場 一美 先生
デジタル・デンティストリーは歯科医療のワークフローを根本的に変えつつある.CAD/CAMを用いたクラウン製作過程のデジタル化はその代表例であり,ロストワックス法による従来型の歯科技工ワークフローがCAD/CAMによるデジタル・ワークフローに取って代わられようとしている.
さらに,口腔内スキャナーを用いて光学印象を行い,モノリシック・マテリアルを用いれば,模型を製作も不要となり,すべての過程をデジタルデータのやりとりで完遂できるモデルフリー・フルデジタル・ワークフローが可能である.こうしたワークフローは当初,クローズなシステムでのみ運用可能であったが,近年,オープン・システムでも可能となったことにより,今後,さらに普及してゆくと予測される.また,有床義歯の分野でもフルデジタル化の試みが行われている.
その結果,治療過程から治療アウトカムまでの形態データがすべてデジタル化され時間的・空間的制限なく共有・利用・保存することが可能となり,いわゆるデータベース基盤型補綴歯科治療が実現される.講演では臨床例を供覧しながら,デジタル・デンティストリーの今後の展開の中でキーとなるデータベース基盤型補綴歯科治療について解説し,デジタル・デンティストリーの未来について皆さんと考察したい.
CAD/CAMシンポジウム
-
スキャナと加工機の精度:原理と実態
株式会社医科歯科技研 代表取締役
藤原 芳生 先生
近年になってようやくデジタルデンティストリが本格化され、 スキャナを始めとしてソフトや加工機とその素材、データの移行システムなどが著しく進化してきました。 技工の全てが口腔内スキャナから始まる時代がすぐそこまで来ています。現在ではすでに、模型を必要としないデータだけによるモデルレス技工も可能となっており、弊社においても全症例の半数近くがモデルレス技工となっています。
スキャナがデジタル・デンティストリーの入り口である限り、そのデータの性質や造形に至るプログラム・アーキテクチャ、あるいは加工機についても知識情報を整理する必要があります。まずさまざまなCAD/CAM機種選択の判断基準となるような原理的な説明を中心にお話したいと思い、デジタル機器の精度的問題、それらの認識についての誤解を解き、 スキャナの根本的欠陥、データの不確実性、CAD/CAMのアナログ性などを明確化したいと考えています。例えば「ポリゴンメッシュ密度が精度を決定する」、「加工機もデジタル機器でありスキャナと同程度の精度を持っている」、「プリントデンチャーはミリングデンチャーよりも精度が悪い」などの誤解です。
そしてできればこれらの問題についての解決策も提示するつもりですが、解決策を講じるなかで弊社ではデスクタイプ・スキャナの使用が減少し、口腔内スキャナをフル活用している実態もお見せしたいと考えています。工夫さえすれば古い口腔内スキャナでもほぼ全て使えるということ、使えないのはその特性を知ることなく、工夫が足りないだけであるということです。また、Automateに関連してAIについても触れる予定です。
結論は「スキャナはデスクタイプからIOSへ」「デジタル機器については謙虚に学ばないと使いこなせない」です。 -
「Digital practice integration using iTero」 アンコールセミナー
インビザライン・ジャパン株式会社
Dr.Ingo Baresel
Align Technology社が販売するiTeroに培われる技術は20年の歴史を有し、IOSを単なる修復物製作利用から、いち早くアライナー矯正への道を切り拓きました。世界中でインビザラインによる患者数は約10.9million人を数え、多くの患者の口腔内の健康に寄与しています。矯正利用のスキャンは40.1 million回を超え、補綴利用のスキャンは8.4 million回を数えます。欧米だけに限らず、日本においても最も導入が加速しているIOSです。
2019年に、新たなテクノロジーがiTeroに加わりました。それが世界初となる、う蝕検出をサポートする、NIRI(Near InfraRed Imaging)テクノロジーです。iTeroElement5DおよびiTeroElement5D Plusで選択可能なこの新たな機能は、口腔内3Dスキャンと同時に隣接面カリエスをも検出可能な機能であります。
このNIRIの搭載で、一度の口腔内スキャンだけで、予防・補綴・矯正へのアプローチが可能となり、高いROI(Return on Investment=投資利益率)を実現しております。本講演では、NIRIテクノロジーについてはもちろん、他社IOSと比較したiTeroの魅力をご説明致します。
※本講演は2019年に行われた、講演をアンコールセミナーとして再編集してお送りいたします。 -
Digital Dentistryの臨床導入とIOS Selection
モリタ MDSC所⻑/デジタルデンティストリースペシャリスト
片野 潤 先生
現在、⻭科機械の新三種の神器と言われているCT,マイクロスコープ,CAD/CAMですがそこにIOSが加わる未来が過ぎそこに来ています
先生方の中にも様々なIOSが出そろい既に使用している方も多いと思います
その一方で購入後うまくスキャンできない、バイトが合わない、マージンが合わない、ラボとの連携がうまくいかない等の問題も多くあり、まだまだアナログ印象に軍配が上がることが現実として多いとの声を伺います
しかし、現在の口腔内スキャナは機能を理解しデジタルコンベンショナルな支台⻭形成とデジタルインプレッション・ミリングの関係について知見を深めステップを守ることで臨床使用に問題ない十分なポテンシャルを発揮することができます
そこで今回はIOS含め現在⻭科医院に混在するデジタル機器が繋がることでどのようなシナジーが生まれるかカタログや誌面ではわかりにくい実臨床のルーティーンやデジタルワークフローをご報告させて頂きます -
矯正歯科治療における3次元デジタル技術の応用
大阪大学大学院⻭学研究科矯正科 講師
谷川 千尋 先生
近年、歯科において、口腔内模型、顔面形態画像、CTなど、3次元デジタル情報の量は急激に増加しています。歯科臨床において、歯・顔・顎の形を3次元的に評価することは重要ですが、3次元画像は2次元画像と比較して分析に手間がかかることから、その活用は限定的でした。AIを用いて形態異常の有無や程度を客観的に判断し、さらに3次元形状予測が可能となれば、医療従事者の負担を軽減するのみならず、患者に安心・安全 な治療を提供する上で有用だと考えています。
そこで、本講演では、矯正歯科治療における3次元解析におけるAIの応用について、お話させていただきたいと思います。本講演が3次元解析を臨床応用する上で皆様のヒントになれば幸いです。
技工士セッション
-
IOSを用いたチェアサイド・ラボサイドとの連携の実際
SHAFT 代表
瓜生田 達也 先生
近年歯科歯科業界に於いて、まだ完全ではないながらもCADCAMシステムを応用した歯科技工が全体的に浸透しつつある状況と言える。そしてそれに伴いチェアサイドでも口腔内スキャナー(IOS)にて採得されたデータを元に補綴装置を製作する機会が年々増加傾向にあり、今後も増加の一途を辿ると予想される。しかしながら欧米諸国に比べIOSの普及率はまだ低く、IOS関連の文献、セミナー等も徐々に増加傾向にはあるが、まだ身近な臨床上での経験値と情報量が不足しているのが現状である。そしてその事が起因し臨床に於いて何かしらのエラーが起こり再製作に至る場合がある。そこで今回は臨床上でのエラーを回避する為の勘所を、シロナコネクト・3Dプリンター等を用いた実際の臨床例をもとにチェアサイド・ラボサイドの両観点から探っていきたいと思う。
特別講演
-
Modern Digital Dentistry -Possibilities and Limitations of the Chairside Application
Ivoclar Vivadent株式会社 Head of Global Education Clinical
Dr. Michael Dieter
Our patients are demanding more esthetic, durable and minimally-invasive restorationsthese days. There is also a strong desire for a one-visit treatmentwithout the need of a temporary restoration. The combination of digitally manufactured all-ceramic restorations and the adhesive cementation technique facilitate long lasting restorations resulting in significant preservation of tooth structure and excellent esthetics meeting the highest patient demands. However, small mistakes in the various clinical steps of the treatment sequence and the manufacturing process can compromise the clinical long-termsuccess of our digitally produced restorations.
Dr. Michael Dieter will present the latest innovations in the chairside digital workflow with a focus on material selection, intraoral scanning and completion of the final restoration. The great potential of the chairside CAD/CAM treatment will be displayed as well as its limitations and the decision to transfer the intraoral scan data to the dental laboratory for further processing. -
Accurate milling of STL's with PrograMill PM7
Ivoclar Vivadent株式会社
Dt. Claudio Joss
Claudio Joss will show and explain the labside workflow after receiving and importing the dentist`s intraoral scan data into the CAD software. The further processing of the data will include the creation of the CAD design and the easy and rapid transfer tothe PrograMill CAM software generating the innovative CAD output format CAM5. To understand the differences between a raw STL and a CAM5 output format the workflows in the CAM software will be shown and explained. The final restoration will be milled fromthe latest Zirconium Oxide material utilizing the PrograMill PM7 and stained & glazed for ultimate esthetics.
CV
Claudio Joss is a certified dental technician. After obtaining his Swiss federal diploma in dental laboratory technology, he worked for various laboratories in Switzerland as an all-round technician, ceramist and laboratory manager. He joined Ivoclar Vivadent in Schaan, Liechtenstein, as Senior Manager Global Education Technical / Digital in January 2009. In this position, he is responsible for the training of third-party commercial organizations (dealers) and customers all over the world as well as for the in-house training of international staff in CAD / CAM products and workflows. In addition, he is in charge of organizing and managing in-house global education meetings. He lectures at international conferences and supports R&D in the development of new products in close collaboration with the marketing and sales departments. -
Digital Impression-Science and Clinic
Digital Impression-Science and Clinic Dentsply Sirona
Andreas Ender Dr. med. dent.
Digital impressions are constantly evolving and thriving more and more into the dental office. Whilest the number of intraoral scanning devices is increasing and updates of current systems happen on a regular base, the question is still how to use these, often expensive, devices to the best effort. Accuracy, ease of use, scanning technique, clinical indication are some of the keywords that always connect with digital impression systems.
The aim of this lecture is to give an actual overview on digital intraoral impression systems. The level of accuracy and the comparison to well established conventional impression techniques will be shown. The clinical indication based on accuracy and scan strategy can then serve as a guideline for the dentist, wether or not use such systems in the dental office right now. -
デジタル オーラル ヘルス & ビタブロック材料の選択基準
白水貿易株式会社/VITA
Dr. med. dent.Stamnitz, Bernhild-Elke
多くの歯科医師よりブロックの選択基準について尋ねられることがあります。 セレックシステムは、例えば長石系VITABLOCS; 仮歯用CAD-TempやハイブリッドセラミックENAMICなどは チェアサイドでの修復作業が可能です。 前歯部修復からインプラント上部体に至るまで、修復のプロセスやマテリアルを 実際に患者に対し説明することが可能です。化学的なマテリアルのデータおよび術者自身の経験に基づいて説明をうけることで、 より今後の方針がクリアになります。 ビタブロックの選択基準を私の臨床経験に基づいて皆様にお話しできればと思います。
-
Esthetic planification in digital era
YOSHIDA/Carestream DENTAL
Dr. Carlo Massimo Saratti
The evolution of adhesive and minimally invasive dentistry allowsto use a wide range of clinical solutions to meet the aesthetic demands of each patient. Often, however, the expectations to be met are so high that they require an in-depth study of the case with the aim of offering arestorative treatment whichintegrates harmoniously the aesthetics of the smile. In this optic, various digital tools have been developed and perfectionatedto provide two-dimensional and three-dimensional treatment previsualization images. This report will illustrate multiple aesthetic clinical cases solved with adhesive and minimally invasive techniques where fully digital workflows and case planning have been integrated.
-
INTRAORALSCANNERでひろがるデジタルデンティストリー
YOSHIDA/MEDIT/高松歯科医院
高松 雄一郎 先生
我が国では、超高齢社会となり歯科医療従事者の減少が危惧されている。より良質な歯科医療を永続的に提供するには、人材の確保とともに生産性の向上を目指す必要性がある。そのひとつの方法としてCAD/CAMを含むデジタル技術の活用があげられる。
COEXi500はオープンシステムの口腔内スキャナーであり、歯科院内のデジタルワークフローに簡単に組み込めるだけでなく、デジタルラボとの連携もスムーズに行うことができる。また、クラウド型管理ソフトウエアであるMeditLinkは、驚くべきスピードでアップデートを繰り返し、さまざまなアプリケーションを追加しながら、リリースからわずか数年の間に大幅な進化を遂げている。
今回は、歯科医院においてデジタルトランスフォーメーションを目指していく中での、当院におけるCOEXi500の活用法を中心にお話したい。「〜抜髄する前に知っていて欲しい〜保存修復から考える⻭髄保護」
ULTRADENT JAPAN株式会社/宮地⻭科医院
宮地 秀彦 先生
う蝕に対する保存修復治療は、G.V.Blackによって100年以上前に確立されたこともあり、現代においてはコンベンショナル、いわゆる“Drill and Fill”な分野と見なされがちです。しかしながら、う蝕進行機序の解明やレジン系⻭質接着システムの信頼性向上などを背景としたMinimal Intervention(MI)コンセプトと共に、直接コンポジットレジン修復として普及しました。その一方で間接法修復においても、⻭科用CAD/CAMシステムをはじめとするデジタルデンティストリーが、その急速な発展にともなって、広く臨床に応用されつつあります。
しかしながら、いずれの術式・器材も正しく選択・適用するためには、それらに関する知識と深い理解が必要であり、それ無くしてコストや時間ばかりを重視した治療が多く行われてしまえば、結果として⻭科医療従事者と患者の双方において、不幸な関係性だけが残ってしまいます。
今回は、私自身の臨床におけるう蝕除去や象牙質コーティングなど、保存修復学的見地より心がけている幾つかのポイントを紹介させていただきたいと考えております。皆さんのご参考になれば幸いです。5G・XR・3DPrinting技術を活用した⻭科領域の遠隔手術支援の実証実験を実施
〜東京と大阪間で、VR・AR映像を通して診断・治療の指導と手術の支援を行う〜なんばアップル⻭科 / 梅田アップル⻭科
林 大智 先生 / 丸尾 瞳子 先生
現在,若い⻭科医師の臨床現場における診断・治療は上級医とのFace to Face が主体をなしている。その多くがクリニック完結型であり、⻭科医師が勤務するクリニックや地域により知識・技術のばらつきを認める。⻭科医師の知識・治療技術向上のためウェブセミナーや勉強会が行われているが、一方的に講演するものであり,Hands On Seminarであっても術式の一部分を切り取ったものであった。そのため若い⻭科医師は新しい知識や技術習得が困難な場合が散見されている。今回我々は⻭科臨床問題に対して5G・XR(※1)・3DPrinting模型を用いた実証実験を経験したので報告する。
※1: VRは医用画像や実写映像、CGアニメーションなどを用いて、人体構造、病態生理、臨床現場などを、臨場感を持って再現した仮想現実のことである。このVRに現実世界を重畳して体験可能になると拡張現実ARとなる。さらにVR環境と現実世界を時間的・空間的に整合し融合した複合現実はMRと呼ばれる。これらを総称してXRと呼ぶ。会員発表
-
One visit treatmentで行ったセラミック修復症例を通しての基礎的な治療ステップの再考
北海道支部/フラワーデンタルクリニック
麻生 雅史 先生
「目的」
近年のデジタル化の流れは歯科診療のスタイルを大きく変化させてきた。当院では2016年にCEREC Omnicamを導入した。導入初期はインレーやクラウンなどの単歯修復のみの活用だったが、現在はコネクトケースセンターを介してラボと連携しロングスパンブリッジや、サージカルガイド、アライナーなど多くの診療で活用できるようになってきた。導入5年目に入った今、基本に立ち返り単歯修復における基本的原則について考察したいと思う。本症例では基本的原則を順守しOne visit treatmentで治療を行い、良好な結果が得られたので報告する。
「症例」
40歳、男性。36に冷水痛を認め治療を希望された。36にCEREC Omnicamを用いてOne visit treatmentでセラミック修復を行なった。
「結果」
基本的原則を順守し治療を進めたことで術後疼痛などの不快症状を認めず、良好な結果が得られた。
「考察及び結論」
今後もIOSの進化はまだまだ続くであろう。しかし、最先端の機械・器具を導入しても良好な治療結果を得るためには基本的原則を順守することが重要と考える。
-
当院におけるプランメカシステムの活用法
北海道支部/五輪通り山口歯科
山口 圭輔 先生
「目的」
現在多くの歯科分野においてデジタル化の流れが加速している。当院では、IOSやミリングマシンを導入しているが、3Dプリンターやファーネスについては導入に至っておらず、院内にて製作可能な補綴物は限られている。そこで、院内で製作しないものについてはクラウドを活用したオープンシステムによりラボとの連携を図っている。今回、当院におけるラボサイドとの連携について報告する。
「設備及びソフトウェア」
院内製作物においては、IOSであるEmeraldTM(Planmeca)を使用。デザインソフトとミリングマシンはPlanmecaのPlanCAD® EasyとPlanMill® 30 Sを使用した。一方で、外注製作においては、EmeraldTMを使用しgooglecloud(google)を活用して、技工所とコミュニケーションをとった。 技工所では、デザインソフトとミリングマシンはexocad(exocad)とinLab MC X5(Dentsply Sirona)を使用した。
「結果」
オープンシステムを利用し技工所と連携し補綴物を製作したが、当初はその完成度に満足できなかった。しかし、デジタル設備とクラウドを活用することで、より迅速にかつ正確に情報を共有することができ、満足できる精度の高い製作物の供給が可能となった。
「考察及び結論」
確立されているクローズドシステムとは違い、各社IOSデータとラボサイドのデザインソフトウェアとの整合性を保つには、お互いに情報の共有や結果のフィードバックが必須であると考える。デジタルでは各種数値(パラメーター)の補正で調整できる。技工所との間でクラウドを活用し情報を共有することは非常に有益であると考える。 今後は院内設備のソフトウェアのアップデートや新たなシステムを積極的に取り入れることでさら なる医院の成長へ繋げたい。 -
エンドクラウンを用いた歯冠長の短い歯冠修復の1例
東北支部/小笠原歯科・矯正歯科
小笠原 正卓 先生
目的
CAD/CAMを用いた歯冠修復の予後について、支台歯の形態は重要な要素である。しかしながら、歯冠長が短く、理想的な支台歯形態が得られない症例については、修復材料の破折を防止するため、一定のクリアランスが必要となり、結果として支台歯形態を妥協的なものにせざるを得ない例が散見される。今回、CAD/CAMを用いたエンドクラウン修復を経験したことから、歯冠長が非常に短い不利な状況下での歯冠修復についてその要件について考察してみたい。
症例
58歳女性。主訴は47の腫脹。診査の結果、47根尖性歯周炎と診断し、根管治療後、歯冠修復を行うことにした。患者は同部に対し金属修復ではなく審美修復を望んだため、CAD/CAMによるハイブリッドレジン(接着:Panavia V5®(クラレノリタケ))のエンドクラウン修復を行うことにした。現在まで3年8ヶ月経過を追っているが特に問題事象は発生していない。
考察
金属を用いた歯冠継続歯など、歯冠修復と支台築造体とポストが一体となった修復は、古くから行われてきたが、垂直性歯根破折の原因となること、接着破壊が容易に起こることなどから現在ではあまり行われなくなった。しかしながら、今回供覧した症例のように、築造と歯冠修復物を別々に作成することが脱離の原因につながるなど、いわゆるエンドクラウンにて対応せざるを得ない症例にどのように対応するのか、様々な議論がある。歯冠修復を行う目的は、歯冠形態を回復することによる機能の改善が主なものだが、根管治療が施された歯にとっては、垂直性歯根破折の原因とならないこと、辺縁漏洩による根管への細菌の再感染を防止することも、要件として求められる。材料学を含めたCAD/CAMの技術の進歩が、通常は困難な歯冠修復も、より良好な予後が期待できるのではないか。
-
失敗しないデジタル外注
東北支部/たかはし歯科医院
大内 優歩 先生
目的・背景
近年、口腔内スキャナーの発達により、ラボへの外注においてもデジタルデータでのオーダーが普及している。2019年より自院でも歯科用CAD/CAMシステム Amanngirrbach ceramill、口腔内スキャナー 3Shape TRIOSを導入しデジタル技工を行っているが、予想以上にデジタルゆえの問題に遭遇し、日々試行錯誤の連続である。
歯科用CAD/CAM装置の進歩はめざましく、マテリアルも急速に進歩している。かつてのジルコニアはフレーム材としてポーセレンを築盛することで審美性を得ており、審美的観点からモノリシックによる審美領域での使用は躊躇されていたが、高透光性ジルコニアが登場したことで、従来では適応が難しいとされていた前歯部においてもモノリシックレストレーションで対処できるようになった。
それらの進歩によりジルコニアは従来の課題をクリアしたかに思えたが、支台歯形成時にメーカー推奨のプロトコル通りの形成では最低の厚みの確保ができない場合があり、強度的ならびに審美的に満足のいく修復物を作製できない場合もあるとの声が技工の現場にはある。
方法
ジルコニア歯冠修復における「形成プロトコル+αの厚み」に着目し、製作時の各ステップの留意点とその対応策について過去のCADデータを元に検討した。
結果
ジルコニアによる審美修復を行う上で適切なクリアランスを確保するには、最終補綴形態をイメージした厚みの確保が重要である。そのために支台歯の削除量だけではなく、マージンラインの明確化と形成面をスムースにする必要があった。
考察
今後、口腔内スキャナーの普及に伴い、デジタル外注を受け入れるラボは増加することが予想される。現時点では明確なデジタル技工の留意点についてのガイドラインは存在しないと思われるが、歯科技工士はハイレベルな設計力に加えて起こりうる問題とそれに対応できる能力を身につける必要がある。また、形成の担い手である歯科医師と作製側の歯科技工士が共通の認識を持つことが必須であり、このような作製側の実情を歯科医師側にも周知することでさらなる円滑な連携や良質な補綴製作が可能となり、最終的に患者満足度の向上にもつながると考える。 -
保険診療でのIOS活用~セミデジタルでのワークフロー
関東甲信越支部/(医)尽誠会 新栄町歯科医院
佐久間 利喜 先生
2021年10月現在、日本の保険診療では口腔内でスキャニングを行い補綴物を制作することは認められていない。しかしながら療養担当規則に則った中でIOSを使用し請求することは可能である。一見矛盾する中で、効率的なワークフローを行い、来るべき保険収載となる日まで当法人で行っているワークフローを会員の皆様と共有し、メリット・デメリットをお伝えしたい。
-
グラデーションを有するジルコニアディスクにおける層の違いが機械的性質に及ぼす影響
関東甲信越支部/⽇本⻭科⼤学⽣命⻭学部⻭科理⼯学講座
⽯⽥祥⼰ 先生,三浦⼤輔 先生,新⾕明一 先生
緒言
本研究ではイットリア含有量の異なるジルコニアを積層して色調と透光性を変化させたグラデーションを有するジルコニアディスクの各層について三点曲げ試験およびビッカース硬さ試験を行い,層の違いが機械的性質に及ぼす影響について検討した.
材料・方法
グラデーションタイプのジルコニアディスク(ZR ルーセントスープラA3,松風,京都)のエナメル層,ボディ層,サービカル層の各層から試験片を切り出し,メーカー指定に従い焼結した.4.0×1.2×25 mmの試験片に対して,ISO 6872:2015に準じて三点曲げ試験を行い、得られた最大荷重から曲げ強さ,応力―ひずみ曲線から曲げ弾性率を算出した.また,10×10×3.0 mmの試験片に対して,ビッカース硬さ試験を行い、圧痕の大きさおよびクラックの⻑さからビッカース硬さおよび破壊靭性値を算出した.繰り返し数は10とし,結果について,一元配置分散分析およびTukeyによる多重比較を行った(α = 0.05).
結果
曲げ強さは,サービカルがエナメルおよびボディより有意に大きくなった(p< 0.01). 曲 げ弾性率は,サービカルがエナメルより有意に大きくなった(p< 0.01). ビ ッ カ ー ス 硬 さ は ,全ての層の間で有意差は認められなかった(p> 0.05). 破 壊 靭 性 値 は,サービカル>ボディ>エナメルの順に有意に大きかった(p< 0.01).
結論
グラデーションディスクの各層で性質が異なり,サービカル層で最も大きい機械的性質を示すことが明らかとなった.しかし,層の違いによる表面硬さへの影響は小さいことが示唆された. -
マテリアルの選択基準
関⻄東海⽀部/医療法人三矢会 池田歯科診療所
池⽥ 祐⼀ 先生
昨今、⻭科用デジタル機器の発展により、使用するマテリアルついても各メーカーから様々な種類が開発され、幅広い症例に対応できる様になってまいりました。一方、実際、臨床の場では、患者の口腔内は個々様々な状況であり、加えて、患者の要求も多岐に渡ることから、それぞれの症例に最適なマテリアルを選択するのに困惑する事もあるかと思われます。光学印象後、修復物を作成する最初の出発点がマテリアルの選択であります。修復物が口腔内に装着された後、その予後を大きく左右する要素であることはご承知の通りです。
マテリアルを選択する際、マテリアル側では、強度、接着、硬度、⻭牙の色調の再現性、等、口腔内側では、支台⻭の状態(マージン部が縁上か否か、色調等)、修復⻭の部位、咬合の状態、更には、制作方法をOne visit treatmentで行うのか否か。等様々な条件を考慮して行う必要があります。今後も、更にマテリアルの種類は増えてくるかと思われます。
そこで、本日は、上記の様なマテリアル選択時の様々な条件を整理した上で、選択基準について皆様と検証していきたいと思います。 -
TRIOS導入で変化した日常診療のデジタル化について。
関西東海支部/カミタニ歯科
神谷 光男 先生
私がTRIOS3を導入したのは日本でTRIOS3の薬事が降りた直後の2017年の春でした。導入当時はデジタル印象だけでも大変興奮していたことを今でも鮮明に覚えています。しかし国内でTRIOS3を使用されている方がいなかった時期でしたので全ての事が、毎日トライ&エラーの繰り返しでした。そして使用しているうちに、印象だけにIOSを使用するのではなく、従来のアナログ作業をデジタルに置き換えられる部分がないかと日々の診療で考え、試行錯誤しながら今日に至っております。3Shapeはもともとオープンシステムを売りにしていた事もあり、導入当初からstlデータで色々な事を提携ラボとチャレンジすることができました。デジタルデータにより診療の可能性が広がったのはもちろん、患者への理解を深めるカウンセリングに使用するなど、現時点における当院で行っている創意工夫を今回簡単にご紹介させて頂きます。
-
フルデジタル修復を目指して~デジタルコアの一考~
九州⽀部/愛デンタルクリニック
植田 愛彦 先生
I目的:歯科用CAD/CAMの普及により失活歯の補綴物はデジタル化が当たり前になったが,未だ支台(コア)はアナログが主流である.完全デジタル化をめざして支台(コア)の作製方法を提案する.
II方法:アナログの支台の脱離症例より原因を考察し,デジタル化のためのIOS,材料および接着材料,形成と接着のプロトコルを提案した.
III結果:IOSでの撮影に適した形成は,感染象牙質を除去して可能な限り太い直径で,応力集中を避けるため歯頸部が極力平面でなだらかにポストのテーパーへ移行して先端の窩底へは再度なだらかに移行する.テーパーは4~8°,10mm以内で複数根の場合は平行性に注意する.材料にグラスファイバー強化型レジンのトリニアとPEKKのペクトン,接着材料にスーパーボンドを使用する.
IV考察および結論:今までのファイバーコアの弱点と言える歯質が脆弱,フェルールが少ない症例に有効である.アナログ間接法よりも時間短縮および適合性が向上し,直接法よりも接着性および曲げ強さが向上している.一体型のため応力に強く,長期的な維持にも有効である.費用と操作性ならトリニア,ブラキサーなどにはペクトンと症例に応じての使い分けが大切である.誰もが簡単により良い結果を出す方法としてデジタルコアを推奨する. -
セレックシステムの遠隔操作の取り組み
九州⽀部/C.Aデンタルクリニック
川上 伸大 先生
セレックシステムは、医院の成長に合わせて周辺機材を追加することにより、規模や方向性に見合った様々な修復物が作成できるようになる。しかし、それぞれの機材は高価なものが多いため、導入に踏み切るには慎重になり成長のタイミングを逃す可能性もある。また、チェアサイドでの作業に特化したカートタイプのセレックプライムスキャンはワンマンオペレーションで行うことを前提としており、複数人が同時に取り扱うには工夫が必要となる。例えば院内歯科技工士がいる場合、どのようにしてセレックプライムスキャンを術者と歯科技工士がシームレスに取り扱うかがポイントになる。今回、一般に流通しているコンピューターソフトを利用して、診療室に設置したセレックプライムスキャンを歯科技工士が技工室にいながら操作できるようにした当院での取り組みを紹介する。
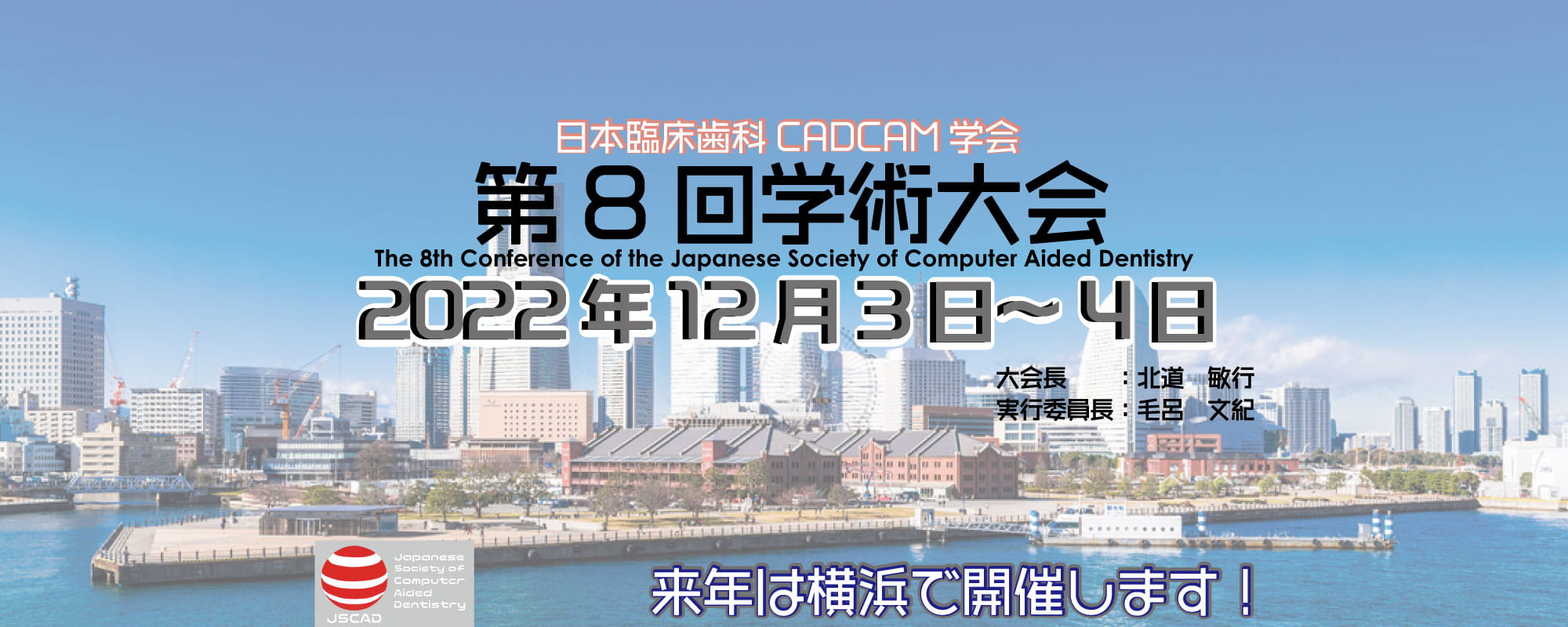
賛助会員